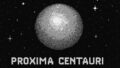Web3.0(ウェブスリー・ポイントゼロ)とは、一言でいうと、「ブロックチェーン技術を土台に、人々が“真に自分のデータや資産を自分で管理できる」分散型のインターネットです。以下、これまでのやり取りで出てきたキーワードも交えながら、段階を追ってわかりやすく解説します。
1. Web1.0 → Web2.0 → Web3.0 の流れ
| 世代 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| Web1.0 | 静的ページ中心。見るだけのインターネット | 初期のホームページ、掲示板 |
| Web2.0 | SNSやクラウドで「参加・投稿」が当たり前に。中央集権的 | Twitter、YouTube、Amazon、Google |
| Web3.0 | ブロックチェーンで「自分のデータ・資産を自分で管理」し、中央に依存しない | Ethereum、Polkadot、DeFi、DAO |
2. Web3.0 のキホン要素
- 分散型ネットワーク(ノードが分散)
たとえばEthereumやPolkadotなど、世界中のコンピュータがネットワークを維持し、一か所の管理者がいません。 - スマートコントラクト(自動契約)
コードで書かれた「もし◯◯が起きたら△△を実行する」という仕組み。DeFi(CompoundやAaveなど)やNFT発行、DAO運営に使われます。 - 自己主権型アイデンティティ
MetaMaskのようなウォレットを使い、メールアドレスやSNSログインではなく、自分の秘密鍵で認証・取引を行います。 - 共有データレイヤー
すべての取引履歴やデータがブロックチェーンに書き込まれ、誰でも平等に参照可能。プラットフォーマーによるデータ囲い込み(Web2.0的スイッチングコスト)はありません。 - トークンエコノミー
プロジェクトごとに発行されるトークン(ERC-20や独自トークン)によって、ガバナンス投票(DAO)やレトロアクティブドロップ、流動性提供(LPトークン)など、経済的インセンティブが設計されます。
3. 具体的な活用例
- DeFi(分散型金融)
Compound/Aave:ETHを担保にUSDCを借りる
Uniswap/Curve:スマートコントラクトで自動マーケットメーカー(AMM)
MakerDAO:ETH担保でDAIを発行 - DAO(分散型自律組織)
トークン保有者がプロジェクトの運営方針を投票で決定 - NFT(非代替性トークン)
アートやゲームアイテム、レピュテーション証明など、唯一無二の資産をブロックチェーンに刻む - レトロアクティブドロップ
過去のオンチェーン貢献を評価して、後からトークンを配布 - DePIN(分散型インフラ)
HeliumやDIMO:IoTやモビリティネットワークを分散型で運営 - クロスチェーン/マルチチェーン
Polkadot/Cosmos:パラチェーンやIBCでチェーン間をつなぎ、完全分散ながら相互運用性を実現
4. Web3.0 がもたらすメリット
- 検閲耐性:誰かの政治的判断や企業の都合でアカウント停止されにくい
- 自己管理:資産やデータを「自分で管理」できる
- オープンイノベーション:誰でもプロトコルを立ち上げ、参加できる
- 公平な報酬設計:レトロアクティブドロップや流動性マイニングで、初期ユーザーにも恩恵が回る
5. 注意すべきリスク
- ガス代(取引手数料):ネットワークの混雑で高騰
- スマートコントラクトのバグ:InsureDAOが保険を提供するほど、リスクが存在
- スキャム・詐欺プロジェクト:情報の見極めが重要
- 税務処理:売却・使用タイミングで課税が発生するため、専門家と要相談
まとめ
Web3.0は「インターネットの民主化」とも言えるテクノロジーです。これまで中央集権的だったサービスから脱却し、自分の資産・データを自分で管理しながら、透明で公正な経済圏に参加できる未来を目指しています。ぜひ、少額からウォレットを作り、dAppsやDeFiを体験してみてください!